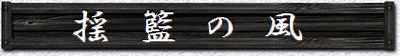
|
二十三. 半日がかりになると思っていた作業は精力的な大工達のおかげで昼前に終了した。状況によっては夕食も用意するつもりでいたのだが、紀一は昼食さえも遠慮して帰ろうとする。 「でもちょうどお昼ですし、大工さん達の分もご飯作ってあるんです」 「でも御代はきちんと受け取ってますから……飯まで頂戴するわけには」 そんな押し問答で謙虚なのか強情なのかちっとも首を縦に振ってくれない紀一に、圭祐は誰か後押ししてくれないかと周りを見渡した。こういう時にさり気なく機転を働かせてくれる隆はもちろん、皓司も先刻浄次と共に城へ呼ばれて不在。 保智は論外、宏幸は手伝いが終わるなりさっそく子分たちと我躯斬龍で遊んでいた。 「でもでも言い合ってんじゃねえよ」 庭の片隅で綺堂と話していた安西がふいに紀一の横っ面へ小石を投げつけた。当たる前に阻止することもできたが、怪我をするような投げ方ではないと判断して圭祐は上げかけた手を引っ込める。紀一がイテッと軽く肩を竦めた。 「いいから食ってけ」 「でもそんな、悠の兄貴」 「俺の頼みが聞けねえんなら金輪際名前で呼ぶな」 「うっ……頼みってほとんど脅しじゃ」 「それに、本音はもう少し一緒にいたいんだろ」 最後の台詞の意味が分からなかったが、紀一は途端に赤面してこちらを見たかと思えばくるりと背を向けてわーっと安西に突進していく。なんだか面白い人だ。 長年畳に慣れてきた隊士達にも板の間は概ね好評だった。 材質が良いのもあるが、わずかの隙間もなくぴっちりと詰められた板並びや木目の揃え方まで一枚一枚計算されているのは素人目でも分かる。端まで丹念に磨き上げられた床の下には、冬場は足が冷えないように、夏場は熱気が篭らないようにと工夫がしてあるらしい。 短時間でここまで丁寧な仕事を成し遂げてくれた九重組にこれからも世話になりたいとお願いすると、紀一は大仰に謙遜しつつもこちらこそ是非と答えてくれた。 「んじゃ綺堂さんと安西さんて黄金期の人なんスか!?」 紅蓮隊の元班長で安西の相方だったと紹介された綺堂は、持ち前の人懐っこさと大らかな口調であっという間に隊士と打ち解けている。 現役の時はどうだったのかと聞かれ、自分達の時代は遠征続きでろくに睡眠も取れなかったが毎日ここでみんなと顔を合わせて食事する時間が一番楽しみだった、と語る大先輩に一同の感慨深い溜息がこぼれた。 しかし綺堂は『黄金期』を知らなかったらしく、その時期の人かと問われて首を傾げる。 「黄金期? すいません、それいつ頃の話?」 「え? だからえーと、先代がバリバリ活躍してて豺狼の群れとか恐れられてて、隠密衆に入りたがる奴が後を絶たなかったとか……そのへんの時代っス」 もっとも、当時から黄金期と謳われていたわけではない。 そういう賞賛は何年も後になってから付いてくるもので、当時の隊士にとっては至って普通の、あるいは人生でもっとも過酷な日々の繰り返しだっただろう。 「んー? だとすると見積もってもせいぜい十年前ですな。俺らちょうど十年前に辞めたんで、その前後でしょう。斗上さんや殿下が全盛期の人ですよ」 自分達は黄金になる前の暗黒時代でしたから、と笑う綺堂に圭祐は疑問符を浮かべた。 隆や皓司と年が近いはずなのに現役の年代がずれている。 二人は共に十六、十七で入隊した。彼らが黄金期の隊士なら綺堂と安西はもっと幼いうちに入隊していなければ暗黒時代とやらは経験できないはずだ。 入隊に年齢制限がないとはいえ、よほど稀な才能でも備えていないかぎり心身共に未熟な十五歳以下は受け付けない。過去にそれ以下の年齢で入隊した稀な才能の持ち主はいなかった。 否、ひとりだけいるか。 自分の年齢を間違えて数えていた巴が。 彼は十七で入隊したが、幼少時に大人の都合で実年齢を三つほど上乗せされていたのが最近発覚したばかりだ。つまり十四で入隊したことになる。当然、彼も黄金期の人だ。 綺堂の言う暗黒時代とは、浄正が宿敵を討てずに辛酸を舐め続けた十三年間のことだろう。 隆も皓司も、ここにいる隊士のほとんどがその期間に生まれた世代。 だから今の隠密衆に当時を経験した隊士は一人もいない。 生き残ってもその後真っ当な余生を送れた者がいない、と言った方が正しいのか。 隊士が次々と戦死するなか幾人かはその時代を生き抜いたと聞く。けれども肉体より先に精神が崩壊し、幻覚や悪夢にうなされながら遠からず廃人になった。 誰ともなく語り継がれてきた風聞が隠密衆の黒い歴史として存在しているだけに過ぎず、真実は浄正や当時の老中だった穂積くらいしか知り得ない。だが城下の墓地に並んだ無数の卒塔婆を見ればそういった話はあながち誇張でもないのだろう。 隊士達は黄金期以外に興味がないようで、誰も矛盾に気づいていなかった。 安西は三十一に見えるならそれでいいと年齢をはぐらかしたままだが、本当に暗黒時代の隊士なら三十一やそこらではおかしい。 「綺堂さん、今おいくつなんですか?」 「俺? 四十二です」 ガタッ、と一同がどよめく。 言葉にされるとさすがに衝撃的で、次の質問がすぐに出てこなかった。 皺ひとつない精悍な顔つきや体格、声の張りや口調、人柄や雰囲気、どれを取っても四十を超えた人の風体ではない。四十代というと浄正のような酸いも甘いも知り尽くした、どこか陰りのある人間を言うのだと思っていた。多少の個体差、経験の差はあるとしても。 「……安西さんとは年が離れてらっしゃるんですか?」 「安西ちゃんは一つ下ですよ。何、本人サバ読んでるんですか?」 「読んでねえよ。連中が勝手に三十一だとか決めつけてるだけだ」 さらにガタッと一同が立ち上がる。 「ちょ、安西さんて……よんじゅういちなんスか!?」 「お兄様の嘘つき! オレの父さんと同い年だなんて……!!」 「見えねえなら永遠にサンジュウイチだと思ってろ」 そういう問題じゃない、と動揺する隊士達を見て綺堂が噴き出した。年齢詐称の云々ではなく衛明館の賑やかさが面白かったらしい。 目を細めて後輩達を眺めている綺堂の横顔にどきりとした。 穏やかな眼差しがほんの一瞬、違うものを見ていたような気がしたのだ。 かつてこの広間には綺堂の知る仲間がいて、こんな風に笑い合ったりもしたのだろう。 そのうちどれほどの仲間を失い、どんな想いでその死を受け止めたのだろうか。 今とは比べようもない時代を生き抜いた人の目に、今の自分達はどう映っているのだろう。 ときどき安西は浄正に似ていると感じることがある。 いつかに見た瀞舟の眼差しもどこか浄正に似ていると思った。 綺堂も、きっと同じだ。 同じ時代、同じ時間を過ごした者がふとした刹那に浮かべる瞳の奥の色を、圭祐はなぜか見てしまう。思い込みや憧憬から生じる想像ではない。たしかにそういう眼差しをするのだ。 隆や皓司はそんな目をしない。沙霧も、今は亡き司も。 「どうした、圭祐」 途切れていた音がふいにざわざわと鼓膜を通り抜けた。じっとこちらを覗き込んでくる安西の顔が近すぎてびっくりする。 「あ、いえ。何でもないです」 「俺が四十過ぎのおっさんでがっかりしたか?」 冗談めかしてにやにやと笑いながら、次いでこう言うのだからずるい。 「何考えてたっていいが今は野暮だろ。らしく振舞っとけ」 ぽんと頭に乗せられた手の重みは、やっぱり隆や皓司のそれとは何かが違った。 |
| 戻る | 進む |
| 目次へ | |